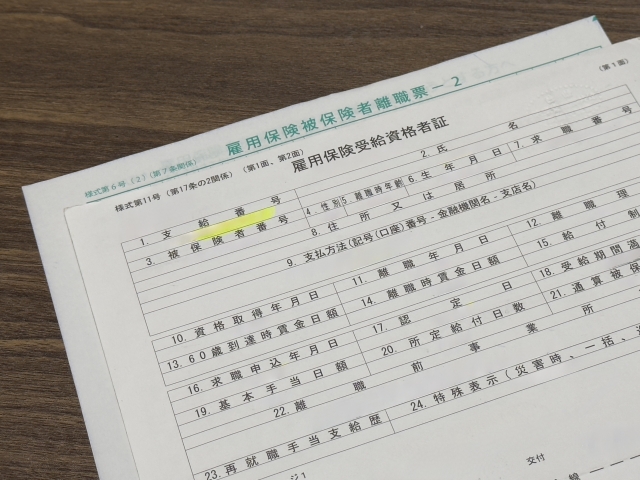退職後は、年金や健康保険など、これまで会社が行っていたことをすべて自分で行う必要があります。とは言っても、具体的に何をすればよいのかわからないという人もいるのではないでしょうか。
ここでは、初めて退職した人向けに、退職したらやることを順番どおりにまとめました。
焦らず、ひとつずつこなしていけば大丈夫。ぜひ参考にしてください。
退職したらやることまとめ
退職したらやることは以下のとおりです。
- 年金の切り替え
- 健康保険の切り替え
- 失業保険給付金の手続き
- 住民税、所得税の支払い
退職後に会社から届く書類まとめ
退職すると、会社からさまざまな書類が届きます。ひとつずつ整理して見ていきましょう。
雇用保険被保険者証
会社の雇用保険に加入していたことを証明する書類です。
退職するまでは会社が保管していますが、退職後は被保険者の元で保管することになります。転職先が決まれば、転職先の会社に提出し保管してもらいます。
健康保険・厚生年金保険資格喪失証明書
加入していた健康保険の資格を失ったことを証明する書類です。国民健康保険の加入手続きに必要です。
源泉徴収票
その年に、会社から支払われた給与・ボーナスや納税額を確認するための書類です。
転職した場合は転職先での年末調整に、転職しない場合は自分で確定申告を行う際に使います。もし届いてないことに気づいたら、すぐに連絡して速やかに送ってもらうようにしましょう。
離職票・退職証明書
失業保険の申請手続きに必要となる書類です。
退職後に会社から郵送されるケースが多いようです。
退職後にやることとは?やることの順番についても解説
では、退職後にやることを順番に解説していきましょう。
①年金の切り替え
退職した会社で厚生年金に加入していた場合、厚生年金を受け取れる資格は自動的に失われるため、国民年金に加入しなければいけません。手続きを行わないと年金に未加入状態となってしまい、将来受け取れる年金が少なくなってしまうおそれがあります。
国民年金の加入は法律で定められていますので、次の転職先が決まっていなかったり、転職するまで1ヵ月以上の空白期間があったりする場合は、退職して14日以内に国民年金への切り替えを行ってください。
年金の切り替えは、市区町村や年金事務所で行うことが可能です。
なお、退職後の再就職先が決まっていれば、転職先で年金の手続きを行ってくれるため、国民年金に切り替える必要はありません。また、親や配偶者の扶養に入る場合は、扶養者の勤務先が手続きを行います。
②健康保険の切り替え
退職した後は、会社で入っていた社会保険には入れなくなりますので、速やかに健康保険に切り替える必要があります。保険に入っていないと、医療費を全額負担しなければいけません。今の状況に合う保険を選び、手続きを行いましょう。
基本的には、以下の3とおりの保険があります。
国民健康保険
独立する場合や無職の場合に入る保険です。住所地の役所で加入の手続きを行います。
任意継続被保険者制度
会社を退職しても、一定の条件を満たすことで、継続して以前加入していた健康保険の被保険者となれる制度です。条件がいくつかあるので、しっかりチェックしたうえで加入するかどうかを決めてください。
家族の健康保険(扶養に入る)
退職後、配偶者や親の健康保険に扶養として入る方法です。
被扶養者となるには、扶養者の収入によって生活していることが条件。扶養者の勤務先に申請して認定を受けると、健康保険証が届きます。
退職証明書や住民票などをもれなく提出し、手続きを円滑に進めましょう。
③失業保険の申請手続き
転職先を決めておらず、退職後に転職活動を行う人や職業訓練を受ける予定の人は、失業保険の申請手続きを行います。
会社から離職票が届いたらすぐに最寄りのハローワークに行き、申請してください。
ハローワークには、離職票や本人確認書類などを持参しましょう。申請すれば雇用保険受給資格者証が発行され、失業保険の受給資格を得られます。
失業保険を受け取るには、転職先が決まっていないこと、積極的に転職活動を行う意思があるかが条件です。退職後すぐに転職できる場合は、失業保険を受け取ることはできません。
なお、失業保険の申請は離職日の翌日から1年以内に行わないと、その効力は失われてしまいます。1年以降は申請ができないので十分に注意しましょう。
退職後のやることについて注意すべき点とは?
退職した後、やることについていくつかの注意点をまとめました。
失業保険を受け取るには一定期間雇用保険に加入していたことが必須
会社を自己都合で退職した場合、失業保険を申請できるのは、離職前の2年間に通算1年以上雇用保険に加入していた人のみに限られます。
また、積極的に転職活動を行う意思があることも条件のひとつであるため、病気や出産などの理由ですぐに働けない場合は申請できないので注意しましょう。
失業保険は申請してすぐに受け取れるわけではない
失業保険は、申請してすぐに受け取れない点にも注意しましょう。
給付が開始されるのは、申請して7日間の待機期間と、さらに1ヵ月の給付制限を終えてからが一般的。ただし、労働者側に問題がある場合は、給付制限が3ヵ月になるケースもあります。
退職理由が倒産など会社都合だったり、教育訓練を受けたりする場合は、給付制限が短くなることもあります。
いずれにせよ、自己都合で退職した場合はすぐに失業保険を受け取れませんので、その間は貯金を使うなど資金計画を立てておく必要があると言えるでしょう。
定期的に転職活動を報告する必要がある
失業保険を受け取るには、ハローワークに定期的に転職活動していることを報告しなければいけません。報告は、原則4週間に1度と決められています。
実績として認められる転職活動は、求人の検索や応募、転職相談などがあります。報告を怠ってしまうと失業保険を受け取れないリスクが生じるので、忘れないようにしてください。
住民税、所得税の支払い
在職中に、給与から天引きされていた住民税や所得税は、退職後は自分で支払う必要があります。
住民税
住民税は、前年の所得をもとに自治体が計算して支払う税金です。
一括払いのほか、年4回の分割払いも可能です。退職後は役所から納税通知書が届くので、そちらを使って支払いましょう。
所得税
所得税は、その年の収入に対してかかる税金です。
所得税は確定申告を行うことで支払額が決まるため、自分で確定申告を行って納めなければいけません。確定申告を行う時期も毎年2月16日から3月15日までと決まっているので、手続きの方法や必要書類なども調べておきましょう。
覚えておくと得すること
退職後、なかなか転職先が決まらず無職の状態が続き、健康保険や国民年金の負担がきつくなったという時は必ず役所に相談することを覚えておきましょう。
場合によっては、健康保険の減免や国民年金の免除・猶予が認められる場合があります。
国民年金は、免除・猶予の手続きをしてから10年間は追納ができますので、就職先が決まってから少しずつ支払うのもよいでしょう。
退職後は税金の負担が大きくなるため支払いが難しくなってしまうケースもありますが、決して放置せず、必ず最寄りの役所などに相談するようにしてください。
やることを整理しひとつずつ取り組んでいこう
退職後は、国民年金への切り替えや失業保険の申請など、手続きをしなければならないことが多くあります。初めて退職した人は、少し混乱してしまうかもしれませんね。
でも、焦らず、ひとつずつクリアしていけば大丈夫です。
この記事でやることをしっかりと理解し、少しずつ取り組んでいきましょう。
エクストでは、警備業や不動産営業など、さまざまな事業を展開しています。
退職後、転職先を探しているのであれば、ぜひ検討してみてはいかがでしょうか。
少しでも気になった人がいれば、ぜひお気軽にお問い合わせください!