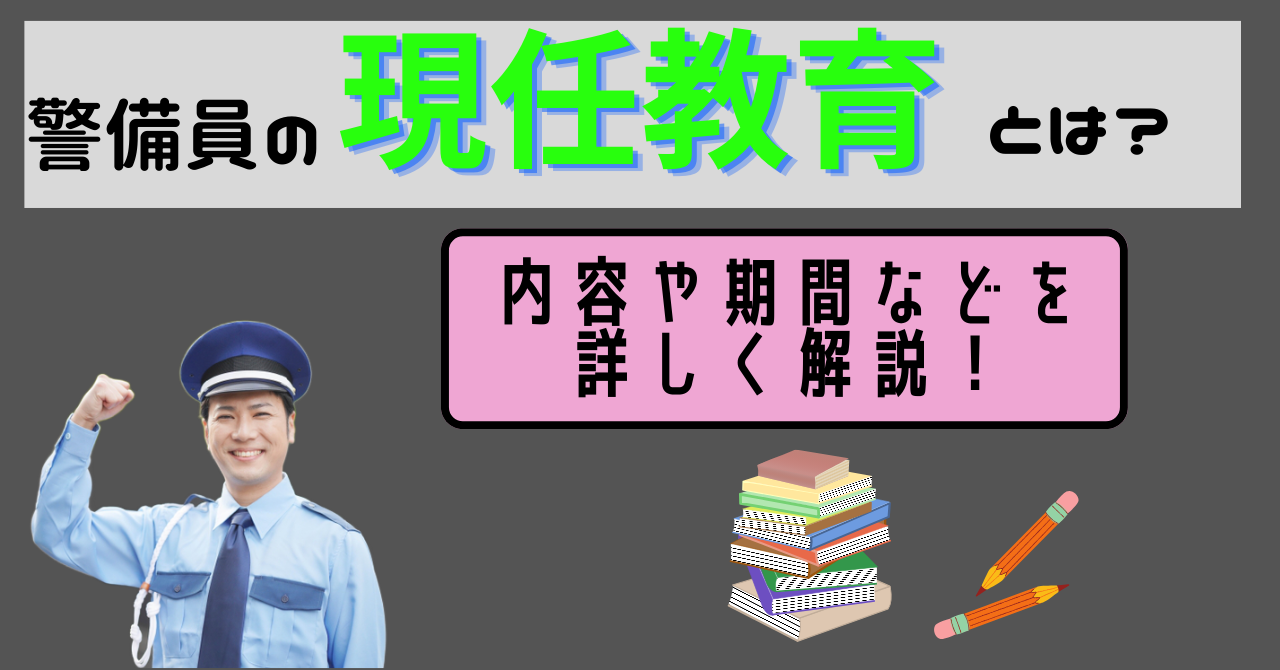現職の警備員は、必ず「現任教育」と呼ばれる定期研修を受けることが法律で決められています。警備業の基本を徹底し、警備員がきちんと法律に従って業務を遂行できるよう、知識や技能を改めて学び直す必要があるからです。
ここでは、現任教育の内容や教育期間などについて詳しくまとめてみました。
 警備マン
警備マン現任教育について知り、モチベーションを上げて研修に臨みましょう!
警備員の「現任教育」とは?
現任教育とは、現職の警備員として働いている人向けの定期研修を指します。
プロの警備員として必要なスキルや知識を改めて学び、警備業務の質を維持・向上させることが目的です。
一方、警備業未経験の人が受ける研修を「新任教育」と呼びます。
現任教育は、社員やアルバイトといった警備員の雇用形態を問わず、警備員全員が受講することが義務付けられています。ただし、警備員ではない営業職や事務職の人は受ける必要はありません。
また、「警備員指導教育責任者」という国家資格を保有している人が講師を担当することも決められています。警備会社では自社の指導教育責任者が教えるケースが多いですが、各都道府県警備業協会といった外部組織に委託することもあるようです。
現任教育では何を学ぶのか
現任教育の内容は「警備業法」という法律で定められており、「基本教育」と「業務別教育」の二つで構成されています。
次の項目から、少し掘り下げて見ていきましょう。
基本教育とは?
基本教育は、警備業務に関する基本的な知識・技能について行う教育です。
施設警備や雑踏警備といった業務区分問わず実施され、以下の教育事項について再確認することが、基本教育で学ぶ内容になっています。
- 警備業務実施の基本原則に関すること
- 警備業法その他警備業務の適正な実施に必要な法令に関すること
- 事故の発生時における警察機関への連絡その他応急の措置に関すること
警備業法第15条が基本原則である警備業。
まずは、15条によって定められている「警備員には特別な権限が与えられていない」こと、「他人の権利及び自由を侵害したり、個人や団体の正当な活動に干渉したりしてはいけない」ことをしっかり確認します。
(※参照元:警備業法 | e-Gov法令検索)
では、教育の内容は、どのようなものなのでしょうか?
具体的に述べると、基本動作や警察機関への連絡の仕方など、基本的な知識の再確認。制服を正しく着ているか、装備品を適切に使用しているかを再点検したり、敬礼や整列などの基本動作の再訓練を行ったりします。
また、事故が起こった際には、負傷者の救護、警察へ引き継ぐための連絡と現場保存を行わなければいけません。事故発生時、スムーズに対処できるよう、改めて基本事項を学びます。
さらに、近年改正された法律を学ぶといった新しい知識の習得、警備のクオリティを向上させるために必要な技能の習得などが挙げられます。
警備業法のほか、憲法や刑法、刑事訴訟法、遺失物法も学ばなければいけません。法律が改正されている場合もあるため、知識のアップデートが必要だからです。



警備業務の基本的な技能や知識を学び直したうえで、さらに新しい知識を習得していく。
これらが、基本教育の内容です。
業務別教育とは?
業務別教育とは、警備業務を正しく的確に行えるよう、各業務についての専門的な知識・技能を習得する教育です。
業務別教育は、すべて講義と実技訓練によって実施されます。
たとえば、1号警備業務について見てみましょう。
1号警備業務とは商業施設や公共施設などの警備業務を指しますが、業務において学ぶ項目は以下のようになっています。
- 警備業務対象施設における人又は車両等の出入の管理の方法に関すること
- 巡回の方法に関すること
- 警報装置その他当該警備業務を実施するために使用する機器の使用方法に関すること
- 不審者又は不審な物件を発見した場合にとるべき措置に関すること
- その他当該警備業務を適正に実施するため必要な知識及び技能に関すること
それぞれの業務や実際の現場で求められる知識を深く学ぶことで、警備員としてよりスキルアップを目指せる教育となっています。
2号業務や3号業務などについても同様。
業務別教育とは、各業務に特化した知識と技能を学ぶ教育なのです。
教育の実施方法や研修方法は警備会社によって異なる
現任教育の内容は法律で決まっているのですが、実施方法や詳しい研修の仕方などは、警備会社によって異なるようです。
実際にあったケースで実践的な教育を行ったり、グループワークで事故やクレームなどについて討論したりなど、それぞれの会社が工夫を凝らして教育を行っています。
以前は対面授業に限られていた研修方法ですが、2019年の法改正により、eラーニングをはじめとしたインターネットの教育方法でも可能になりました。
スケジュールがなかなか合わない人でもオンラインで受講でき、警備員と会社、双方の負担を軽減することが可能です。
現任教育の教育期間は?
資格を保有していない警備員は、基本教育と業務別教育をトータルで「10時間以上」受けなければいけないことが決まっています。
「年間で最低限、10時間以上」という意味なので、一度で10時間も行う必要はありません。
2回にわけて実施する会社が多いようです。
現任教育について知っておきたいこと
現任教育で学ぶ内容や時間のほかにも知っておきたいことについてまとめました。
給料はどうなる?
現任教育は法律で定められた研修なので、受けている時間は労働時間と見なされ、給料が支払われます。会社側からすると、最低賃金以上の給料を支払う必要があります。
給与明細をチェックし、もし給料が少ないと感じた場合、すぐに会社に確認するとよいでしょう。支払われていない場合は法律違反となります。
教育を受ける際の服装は?
では、教育を受ける際、服装はどうすればよいのでしょうか。
自社で行われる現任教育に関しては、制服を着用して受けましょう。
警備業協会で受ける場合は、都道府県によって異なります。私服でよいところもあれば、各社の制服を指定してくるところもあります。
注意しなければならないケースは、私服で受ける場合。
警備員としてふさわしい服装と決められています。Tシャツやジーンズ、ハーフパンツ、サンダルなど、カジュアルすぎる服装はふさわしくありません。
服装にも気をつけて教育に臨みましょう。
教育期間が短くなるケースもある
前述したとおり、資格のない警備員の教育時間は、基本教育と業務別教育を合計して「10時間以上」と定められています。
しかし、現任教育に関しては、資格の有無などによって教育期間が短くなるケースもあります。
たとえば、「警備業務検定」「警備員指導教育責任者」といった警備員資格を保有している場合。
1号警備の「警備業務検定1級」を持っている人が1号警備業務に就く際、現任教育の基本教育・業務別教育ともに免除になります。
1号警備業務以外、つまり交通警備や雑踏警備などに就く際には、先ほどと同様、現任教育の基本教育は免除になり、業務別教育については「6時間以上」と通常よりも短縮されます。
資格を持っている場合は、教育が免除あるいは教育の時間が短縮されることを覚えておくとよいでしょう。
まとめ
現任教育は、現職の警備員として働いている人のための定期研修です。
新任教育よりも専門的で深い技能と知識を学ぶ研修であり、必ず受けなければいけないと法律で定められています。
教育期間は基本10時間と短いですが、資格の有無などによって、教育が免除あるいは教育期間が短くなるケースもあります。
現任教育は、法律を新たに学び直したり、警備員に必要な基本的スキルを改めて学習したりと、専門知識や技能を向上させてステップアップできる機会だと言ってよいでしょう。



このサイトでは、チャレンジ精神のある警備員を募集しています。
ぜひ気軽にお問い合わせください。